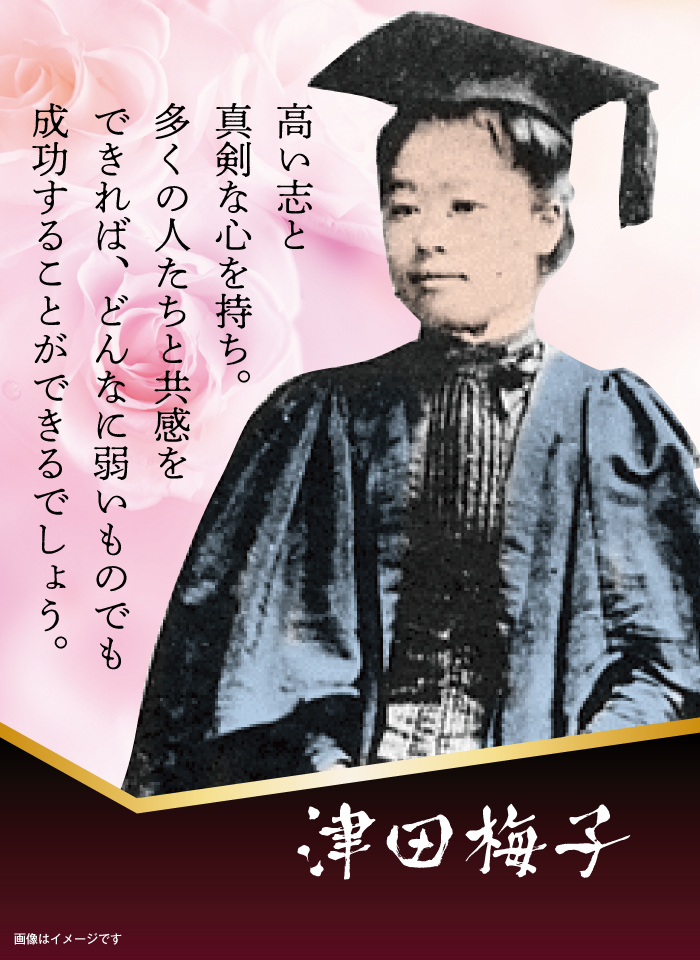(不幸だな)と、竜馬はおもった。
竜馬が行く8 p12
乙女の鬱屈が、であった。それほどの自分をかかえて、いささかもその自分を行動で表現することなく、実家の奥の一室でむなしく歳月を消費しつづけてゆかねばならないのはよほどつらいことにちがいない。
6歳でアメリカ留学
津田梅子は、元治元年12月3日(1864年12月31日)元佐倉藩の藩士で農学者津田仙(つだせん)の子として江戸に生まれました。初名は津田むめ。
父の津田仙は、江戸幕府のて外国奉行支配通弁(通訳官)を務めていました。
明治維新後、津田仙は北海道開拓使の嘱託技術員となります。上司の黒田清隆が「岩倉使節団に女子も連れて行きたい」というプランを考えて、津田仙の娘を推薦しました。
6歳(数え年8歳)の梅子は、北海道開拓使が募集した最初の女子留学生の一人として岩倉使節団(いわくらしせつだん)に加わり、明治4年11月12日アメリカへ出発することとなりました。

このときの留学生で5人の女子がいましたが、梅子は最年少で、英語の単語を2、3語ほど知っている程度でした。アメリカで留学したものの、梅子の留学の最後まで一緒にいたのは山川捨松、永井繁、津田梅子の3人となりました。
アメリカで小学校を終え、女学校にも進み、フランス語やラテン語、数学、物理学、天文学などを学びぶなど、11年間アメリカで暮らしました。
8歳のときには、キリスト教の洗礼も受けています。
19歳の時に帰国した梅子は、すっかり日本語を忘れていて家族に挨拶をするにも苦労したといいます。
人力車に乗ろうとした際には行き先を日本語で伝えられず、通りかかった外国人に英語で通訳してもらったそうです。(幕末維新人物大辞典より)
日本に帰国している留学仲間は就職もままならないため、結婚という道を選ぶしかありません。
梅子も見合い結婚を勧められましたが「愛のない結婚はできない」と断っていました。
大山捨松
留学仲間の山川捨松は、17歳年上の陸軍卿・大山巌の後妻になります。
開国直後で諸外国との交流が進む中、会食などの折りに夫人同伴の必要が生まれました。即戦力となる芸者を正妻として同伴する人もいましたが、山川捨松は留学の知識と英・仏・ドイツ語での会話や本場仕込みの立居振る舞いで応対できるので、「鹿鳴館の貴婦人」と呼ばれます。
鹿鳴館での交流を元に慈善事業などにかかわっていきました。
女子教育ためにアメリカへ2度目の留学
明治22年(1889年)7月にふたたびアメリカ留学して、生物学と教育学の研究に打ち込みます。
当時アメリカで活躍していた女性たちとも交流
ヘレン・ケラー(目と耳が不自由でも障害者の教育・福祉の発展に尽力)
ナイチンゲール(「クリミアの天使」と呼ばれる看護師から看護教育学者、アメリカでは統計学者として活躍。)など (地味スゴ歴史人物伝より)
女子のアメリカ留学のために
「日本婦人米国奨学金制度」作りを思い立った梅子は、資金作りのために帰国前の1年あまりで寄付金集めに奔走。この募金で約30年で25人の女性をアメリカ留学させました。
奨学金で学んだ彼女らも、帰国後は日本の女性教育に大きく貢献することになります。
2度目のアメリカ留学では3年間生物学を学びます。一度帰国後、今度は渡英して高等女子教育機関をしさつするなど、女子教育の基礎を精力的に学びます。
そして「日本の女子教育に力を尽くそう」と決意しました。
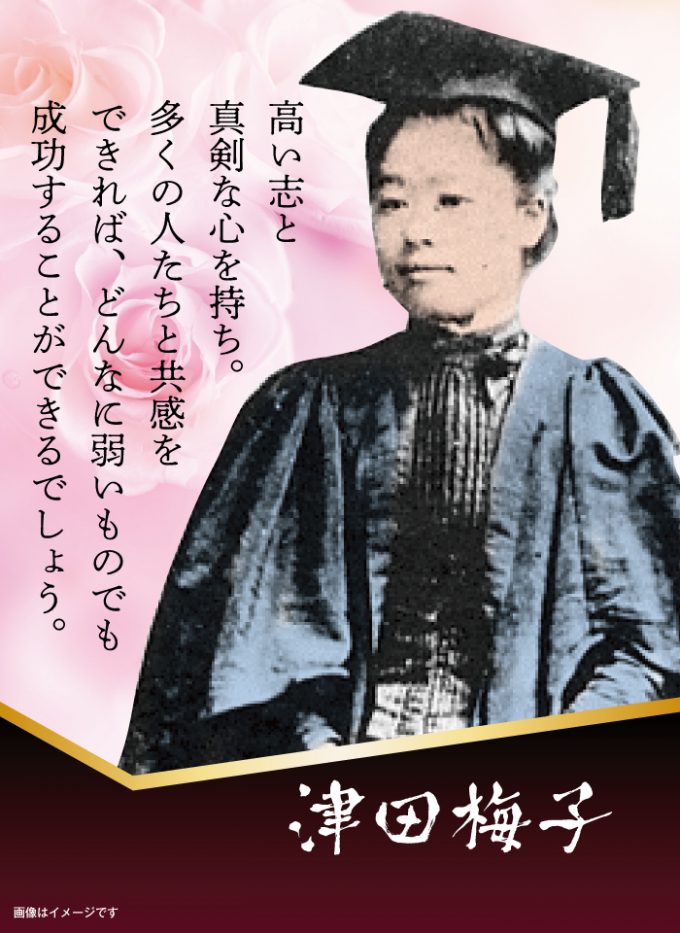
女子英学塾創立
帰国後、女子高等師範学校などで教鞭を執っていましたが、明治33年(1900年)学問を志す女性なら誰でも学ぶことができる目的で、「女子英学塾」を設立。女子にも自由で高いレベルの授業を行いました。
初年度から10人が入学しましたが、教育レベルが高すぎてついていけない生徒が続出するぐらいでした。
教える先生が揃わなかったり、続けていく資金が回らなかったり苦労の連続でしたが、大川捨松をはじめとするアメリカ留学時の仲間やアメリカでお世話になった人たちの協力でなんとか軌道に乗るように。
1904年に「社団法人女子英学塾」の設立許可により社団法人に移行。塾は私立女子教育機関としては初めて、無試験検定による英語教員免許状の授与権を許可されました。
これが、のちに津田塾大学となります。
伊藤博文と梅子
岩倉使節団で一緒に渡米した伊藤博文と再会した折に、下田歌子を紹介されます。彼女は、華族子女を対象にした教育を行う私塾・桃夭女塾を開設しており、梅子は「華族女学校」で英語教師となりました。しかし、桃夭女塾は上流階級の子女に西洋式マナーを教える学校であり、梅が望む教育の場とは違っていました。
桃夭女塾は後に実践女子大学となります。
伊藤博文の子供の英語教師として伊藤家で一緒に暮らす時期がありましたが、伊藤が実は女好きで、妾(めかけ)をかかえていることや、その子供を引き取って正妻に育てさせている事を知り、教育を受けたアメリカの男女の考え方との違いの大きさに驚き失望したと言われています。
YTB どこまで言って委員会 2022.2月より
令和6年7月、5000円紙幣に
2024.4.7追記

生涯を通じて、女性の地位向上と女子教育に尽力した教育家として、津田梅子が新しい五千円札の肖像に選ばれました。
新紙幣には、偽造防止の様々な仕掛けが施されています。
中央左側にはストライプ型のホログラムを採用。3Dで表現された肖像が回転する最先端技術を用いています。この技術の銀行券への採用は世界初です。
角度によって5000の文字やNIPPONの文字が浮かび上がったり、うっすら紫色が浮かんできたりと、実際に手にしないと分からない工夫が織り込まれています。
漢数字の「五千円」よりもアラビア数字の「5000」を大きく配置したのも今回の紙幣から。ユニバーサルデザインとしての配慮となります。
キャッシュレス化が進んでいる令和ですが、ぜひ手に取って確かめてみたいですね。